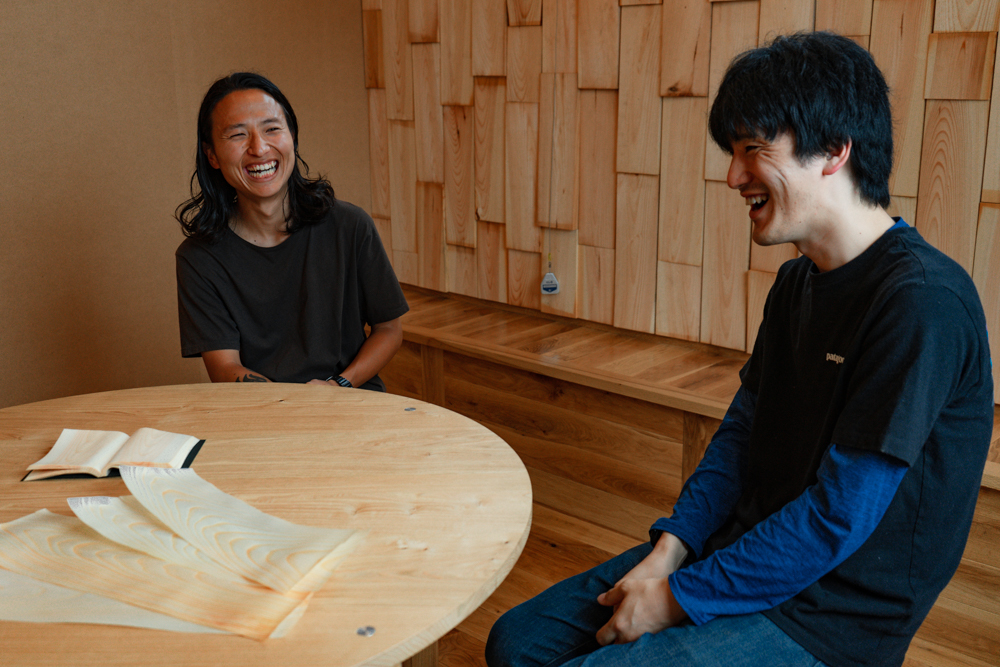「自然とともに日常を営む」
この思いのもとに、Backpackers' Japanは2022年9月15日、長野県の八ヶ岳エリアにキャンプフィールド「ist」をオープンします。
istは、一般的にキャンプと紐づけて考えられるレジャーやアクティビティといった非日常的な体験ではなく、音楽を聴いたり、コーヒーを飲んだり、友達と語りあったり、といった“日常”を自然の中で楽しむことを大切にしたキャンプフィールドです。
istの中には20平米ほどの小さな家、「Hut」があります。Hutには、普段の家での暮らしのように料理をつくることのできるキッチンや、ゆったりと眠りにつけるマットレス付きの寝室スペースがあり、Wi-Fiの良好な環境で仕事をすることもできるなど、日頃の生活スタイルを大きく変えることなく、日常の延長のままに自然の中で過ごすことを可能にしています。
istが、自然を通じた非日常的な体験ではなく、「いつもの暮らし」を送れる場所を目指した理由。そこには、事業責任者・興絽泰明(こうろきやすあき)さんの「本来はもっと身近なものであるはずの自然と人との距離が、多くの人にとって遠いものと思われている」という感覚がありました。

「本来、人と自然を別物として考えるような対極にある存在でもなく、決して対立するような関係性でもなかった。僕たち人も、同じ自然としてのとても広い枠組みに入っていた。しかし街の暮らしが長くなり自然に触れる機会も少なくなると、どうしてもどこか遠い話に聞こえる気がしていた。きっと環境問題の話も同じように思う人がいるのではないかな」
引用元:「自然のなかで暮らしを営む」興絽泰明|note(2021年8月28日)
「少し離れた場所にある雄大な自然も、街中で見かける小さな自然も、私たちの周りにある確かな自然です。僕たちは遠くの自然と近くの自然を区別せず、同じ自然として感じ取れる心の状態をつくりたい」
引用元:「八ヶ岳の麓で、自然とつながるキャンプ場を」興絽泰明|note(2021年4月24日)
istには、「istで自然と時間をともにした人たちが普段の暮らしへと戻っても、自然を一時の非日常として忘れてしまうのではなく、身近なものとして感じてほしい。それにより、より豊かな毎日を送ってほしい」という興梠さんの思いが込められています。
 Photo by Syuheiinoue
Photo by Syuheiinoue
同じ長野で、森の資源を使った豊かな暮らしを提案している株式会社やまとわ(以下、やまとわ)の奥田悠史さんも、「人と自然の距離が遠い」という感覚を持っていると言います。
森と暮らしを再びつないでいくため、夏は農業、冬は林業を営みながら、地域の森林資源を使った家具づくりや家づくり、木のエネルギーを利用した暮らしの提案をするなど、やまとわの取り組みは多岐に渡ります。
ふたりが話してくれたのは、「人と自然の距離が適切になると、日常に能動性を取り戻すことができる。能動的なよき消費者になることで、よりよい社会になるのでは?」というお話でした。それは一体、どういうことなのか? 私たちの普段の暮らしが豊かになるヒントを、聞いてきました。
(企画:なかごみ / 取材・執筆:小山内彩希/取材・編集:くいしん/ 撮影:松田鉄矢)
捻じ曲げられ、日常と切り離される「人と自然」

── 興梠さんと奥田さんは「人と自然が遠い」という感覚を共にしているということを興梠さんから伺っているのですが、「人と自然が遠い」とは一体、どういうことですか?
興梠 僕が以前やまとわさんへ伺ったときに、その話をしたんですよね。
奥田 その時も話したかもしれないですが、僕は世の中、至るところで環境問題や災害について語られているわりには、自然に関心が薄い人がほとんどだと感じていて。それゆえに自然の大切さや価値を伝えるのは、今の時代、すごく難しいことだなと思っています。
興梠 僕も、子どもの頃から海や山など自然の中で遊ぶことは好きだったんですけど、森の循環と自分の命のつながりを実感できるようになったのは、istを立ち上げるために東京から長野に拠点を移してからでした。
「森に降った雨が土の中に落ち、そこから土の中でどんどん水が浄化されて川へと流れ、僕たちが得る飲み水へとつながっている。だから、どこかの生態系のシステムが崩れたら、僕たちの暮らしや命そのものまで脅かされてしまう」といったような実感を持てたのは、自分自身が自然を相手にした事業を始めてからだと思います。
奥田 自分の中に自然と命のつながりを感じられていると、自然が大切だって話はスッと受け入れられるけど、そうじゃないと難しいというのはありますよね。興梠さんが言うように、自然ってそもそも人間を含めた多くの命の源であるから、その豊かさを損なわないようにしたいという思いは僕も共通していて。
その上で、やまとわのことを話せば、「そもそも森ってすごいエコシステム」という認識があって、だから豊かな森づくりをしたいという思いへとつながっています。

興梠 森はすごいエコシステム?
奥田 森にはいろんな生き物がいるけれど、それぞれがポジティブな方向に活動した結果、持続可能性が担保されているという仕組みがすごくおもしろいと感じているんですよね。
人間社会は誰かが我慢しないと維持できないのに、森にはたとえば、葉っぱの食べたい生き物がいて、その葉っぱを食べた生き物の糞を食べたい生き物がいる、そういうポジティブな流れで成り立っている。「森とは、なんていい社会なんだ!」というのが僕の根っこにあります。
興梠 おもしろい。
奥田 また、僕は子どもの頃から家の近くの川で遊び、よく岩場で切り傷をつくってきたんです。こういったことも思い返してみると、自然はおおらかで僕らを包み込んでくれる反面、一歩間違ったことをすれば命を落としかねないほど危険なものでもあるから、適切な近さで共生していかないといけないんじゃないのかな、と思うのですけど。
興梠 共感します。僕も趣味のダイビングで、二十歳のときに海の中で過呼吸になって死にかけた経験があるので(笑)。でも、人と自然が近かった頃は、こういった危険な面も、豊かさを与えてくれる面も、全部ひっくるめて当然のこととして受け止められていたんでしょうね。
奥田 それがあまりにも人間の都合で捻じ曲げられて、その結果、こちらの命まで脅かされることになっているのが、現状なんじゃないかと思います。
たとえば長野でも、もともとは溢れた水が溜まるように水の逃げ道になっていた場所があって、そこでは災害は何十年に1回あるかないかくらいと言われていたんです。だからなのか、その場所を住宅の分譲地にして、家をたくさん建てていった。すると、一昨年の台風で川が氾濫したとき、水の逃げ場がなくなって近隣住宅や畑含めて浸水しちゃうということが起きてしまって……。
滔々(とうとう)と続いてきた自然の流れを変えていくことで、失われていく価値とか文化、自然と共生していた知恵とかもなくなっていくことに、自然と人の付き合い方への違和感を抱いています。
興梠さんの思う、人と自然の遠さとは?
興梠 僕が思っているのは、日常の中で自然は本来とても身近なもののはずなのに、多くの人たちにとって自然は暮らしと切り離されたものとされている感覚があって。
僕は、自然の中で風が好きなんですけど、それもダイビングから来ていて、ダイビングスポットまで船で移動しているときに「甲板に上がると風がめちゃくちゃ気持ちいい」と気づいたことからなんですよね。
でも風って、都会にいても吹くもので、たとえば部屋の窓を開けたり、自転車で走っていても、「風が気持ちいいな」と感じられたりする。そういうふうに自然って暮らしの近くにあるものなはずなんですけど、なにか自然って自分たちの暮らしの外にある非日常的なものとして見られているような感覚があります。

人と自然をつなぎ直したい
── そもそも、私たちと自然はどうして離れてしまったのでしょうか?
奥田 僕は、生活様式の変化が大きく関係していると思います。
昔は薪割りをして薪風呂をしたり、あるいは薪から火を起こして米を炊いていたので、森がなければ営みそのものが成り立たなかったわけです。でも、グローバリゼーションが進み、灯油やプロパンガスなど地下資源に代替されていったことで、森がなくても生きていける社会になったことが、人と自然が離れていった背景にあると思っています。
とはいえ、それは一概に悪いとは言えない話で。
興梠 みんながもっと便利になる必要があって、それを進めていった結果であるとも言えますもんね。
奥田 そうなんですよね。便利にしていく過程で環境破壊が進んでいたとしても、みんなの生活はより便利になって、幸せだった時代があったと思うんですよ。
だって、そうなる以前の、おじいさんとおばあさんが芝刈りへ……みたいな日本昔話的な生活って、想像するだけで肉体的に辛いじゃないですか。土地を持っている人はよかったけど、土地がなくて薪が足りない人はひもじい生活を余儀なくされていたようなこともあったわけなので。
とは言え、今は自然を人間の都合で変えすぎたことで日常生活が脅かされるような被害が出たり、あるいは、海外の自然豊かな土地で過剰な森林伐採が行われて木材の生産に伴う人権侵害も問題とされるなど、社会として整合性が取れなくなっていっている。そういった中で、人と自然の関係性をもう一度いい形につなぎ直して、次の時代に行くために何をするべきか考えていくのが、今なのかなと思っています。

興梠 便利さを求めて自然と距離が離れたというのは、共感する部分があります。僕は人と自然が離れてしまった理由は、都市化が進んで人と自然が物理的に遠くなり、自然に触れる機会が少なくなったことにあるような気がしていて。
自分自身のことをふり返っても、地元・滋賀にいた頃は琵琶湖も近くて、バス釣りとかもよくしていたんです。でも大学生になり、大阪や東京に出てからは自然と離れてしまったなという感じがして。それでもキャンプとか、アウトドアとか、リゾートとか、「自然を感じられる便利なサービスがたくさんあるじゃん!」って話になると思うんですけど、でも土日を使ってどこか遠い所に行って自然と遊ぶと、想像以上に疲れるんですよね。
もちろん僕はダイビングが好きなので、アウトドア自体は好きなんですけど。
奥田 僕もそこは一緒で、リゾートやアウトドアは好きです。でも、疲れる疲れないの話で言ったら、たしかに体力は必要ですよね。
興梠 それをやって次の日から仕事だってなると、もうハードじゃないですか。そうなると、「自然が気持ちよかったな」という体験をしても、「でも家は家でゆっくりできていいな」というふうに、限りなく100から0に戻ってしまうというか、自然と日常がつながらず遠いまま、また毎日が始まっていく。

興梠 でも、先ほどの繰り返しになりますけど、そもそも自然を外に求めなくても僕たちの日常の中にも意識されていないだけで、自然ってたくさんあるんですよね。
であるなら、そもそも日常の中にある自然に気づけたり、あるいは日常の中に自然を取り込めたら、僕たちの毎日はもっとより良いものになるんじゃないかと思ったんです。
── そもそも日常の中で自然が意識されていないことに、興梠さんはどんな問題意識があるのですか?
興梠 自分の中では、身の回りの自然と環境問題がつながっていて、身近な自然に意識が働かないことがいろんな問題を自分ごと化できていない状況につながっていると考えているのですけど。
でもistは、そういう問題意識を起点にして事業をつくっているわけではないんです。「環境問題が自分ごと化できていない」という話から入ってしまうと、小難しいし、「暮らしの中の自然を通して気持ちいい感覚を増やしてほしい」という本当に伝えたいことが伝わりづらくなっちゃう。それにやっぱり、自然のためにやる事業じゃなくて、「人のために」自然と共生する事業っていうところを、ブラしたくないんですよね。
なのでistは、「もっと僕たちの日常にアプローチしていきたい」という思いが一番最初にあって、レジャーやアクティビティーといった一般的なキャンプで想像される非日常的な体験ではなく、自然の中での日常的な体験を提案する形になっています。istを通して「自然の中で過ごすことっていいな」と思ってもらえる人が増えていくと、おのずと環境問題に関心がなかった人も、そこに意識が向くようになるんじゃないかという期待もありますね。

Photo by Syuheiinoue
日常に能動性を取り戻す
── istで体験できる普段の暮らしとはどういったものでしょうか?
興梠 istの中でつくってきたものに、「Hut」という20平米の小さな家があります。Hutにはキッチンやソファ、寝室スペースがあり、Wi-Fiも通っていて仕事もできる。そこで普段の暮らしが営めるようになっています。
ほかにも、カフェやバーラウンジもつくっており、そういった交流地点を通して、自然を語ったり、誰かと共有し合う仕組みをつくっていきたいと考えています。そうやって自分ごととして話すことで、istから戻った日常の中でも、より自然とつながっている実感が得れるんじゃないかなと。「キャンプ気持ちよかったな、終わり」とならないような仕組みづくりですね。
たとえばですけど、僕を含めてistをつくってきたスタッフが3人いるのですが、全員が拠点を青木の平キャンプ場に拠点を移し、1年間かけて自然の移ろいや特徴をそれぞれの視点で見てきました。実際にカフェやバーに立つ僕らがそれを語るだけでも、訪れる人の視野はぐっと広がると思うんです。
 Photo by Syuheiinoue ※記事内で使用している風景写真はすべてist場内、および周辺でのものです
Photo by Syuheiinoue ※記事内で使用している風景写真はすべてist場内、および周辺でのものです
奥田 興梠さんが訪れた人に伝えたいことは、たとえばどういったことですか?
興梠 僕たちは移り住むまで、自然が一番気持ちよく感じる季節は夏だと思っていたんですよ。涼しくて高原の緑も豊かだろう、ということで。そして、もっとも厳しいと思っていた季節は冬だったんです。マイナス20度まで気温が下がることもあると聞いて、体感する前から震え上がっていました(笑)
でも暮らしてみて、僕は、冬の自然が一番好きだなと感じたんです。
気温がマイナス20度まで下がるからか、空が絵の具で塗った青みたいな、見たこともないくらい澄んだ色をしていることがわかったんです。近くの八ヶ岳も雪化粧がかかってパリッとした白銀の景色になるし、春夏秋は基本的に動物がいるから何かしらの音がするんですけど、冬はそういった景色の中で静寂を楽しむことができるということもできる特別な時間だなと。
そういうふうに、スタッフが自分だけが語れることを伝えていったら、Hutを利用する人たちが窓の景色に目をやることにつながっていくと思うし、日常に戻ったときにもHutで過ごしたのと同じように、身の回りの自然に対して感性が働くんじゃないかと思うんですよね。
 Photo by 本間貴裕
Photo by 本間貴裕
奥田 日常に戻ってきたとき、身の回りのどんな自然に対して心が動くようになると思いますか?
興梠 たとえばスーパーに並んでいる野菜とか魚、あるいは花屋の植物でも、それぞれ四季によって旬のものが全然違って、本来はすごく季節や風土を感じられるものだと思うんですよね。
今まで値段の安いものや広告されたものを手に取りがちだった人も、istから日常に戻ってきたときに、そういったものに四季の移ろいを感じながら手に取れるようになってもらえたらいいなと想像しています。
奥田 それってすごく能動的な消費ですよね。
というのも、そもそも僕たちの日常って、情報化社会が発展してきたことで、知らず知らずのうちに受動的にさせられてきたんじゃないかと思っていて。アナウンスされたものを選んで、消費するというスタイルが染み付いているような気がするんです。

── 受動的な消費よりも能動的な消費がいいというのは、どういう意味でしょうか?
奥田 僕が、能動的な消費がいいなと思うのは、そもそも、どうすればよき消費者になれるだろう?ということに興味があったからです。ものづくりの背景をちゃんと知っているかとか、環境に負荷がないかとか、誰かが犠牲になっていないかとか、そういうことを考えて選べる消費者にどうすればなれるかと、よき消費者を観察していったとき、「よき消費者はよきものの作り手であることが多い」ということに気づいたんです。
つくるというのは、とても能動的な行為ですよね。そう考えたとき、能動的に生きるということが、よき消費者への道なのではないかと思いました。そして、よき消費者が、よき社会をつくるというふうにつながっていくのではないかと。
興梠 能動的な自分とよりよい社会がつながっているという視点はおもしろいです。
奥田 社会という大きな話をしないでも、個人レベルでも能動的な方が、暮らしが豊かになるんじゃないかと思っています。受動的にあらゆるサービスや商品を消費することで、思考する力が失われていないか?と思うからです。たとえば、昔の人は壊れたら自分の手で直したり、もっといいものをつくろうとしたりしたと思うんですけど、現代の人たちは「壊れたら交換すればいいや」という思考に偏っていないか、ということです。
人間は考えることを通じてたくましく進化してきたわけで、人として自分で自分の心地よさを考えることをやめてしまったら、もったいないじゃないですか。
興梠 なるほど。自然の中にいると、自然って美しくて気持ちいいものというだけでなく、命を脅かす危険もあるものだから、能動的にならざるを得ないという側面もあると思います。
奥田 たしかに。そういう意味では、自然の中で過ごすことは自分の中の能動性を取り戻すためのいいトレーニングかもしれないですね。

自然の中で過ごす「文脈」を増やしていきたい
── istは、これからどんなふうに人を呼び、訪れた人たちが自然に関心を持つことにつなげていきたいですか?
興梠 それこそ、やまとわで森の資源を使った家具づくりなどを通して、すでに僕たちの暮らしにアプローチをしている奥田さんから、何かアドバイスをいただきたいなと思っていて。
奥田 僕は、「コンテクスト(文脈)」と「リレーション(関係性)」を大切にしてアプローチしていくのがいいのではないかなと思っています。なぜなら最初のお話に戻りますけど、自然に関心の薄い人が多いことを前提にすると、森がいいなと思って森に来る人って多くはないんですよね。
だからこそ、森でコーヒーを飲もうとか、キャンプをしようとか、好きなもののフィールドとして森を使うような文脈を混ぜて、森自体への関心や森と自分を考えることへとつなげていくのがいいのかなと。
興梠 自然の価値をそのまま伝えるのは、すごく難しいからこそ入り口が大切ということですよね。
 ▲奥田さんにやまとわの工房内を案内してもらった
▲奥田さんにやまとわの工房内を案内してもらった
奥田 難しいし伝わりづらいからこそ、やまとわはポップさをすごく大切にしています。森の話をフロントに置くよりも、こういう家具を使ったらおもしろかったり、うれしかったりするんじゃないか、という提案を一番見えるところに置くということですね。
たとえばこのノートブックも、経木という材木を使っているんですけど、経木とは木を紙のように薄く削った材木で、一般的には包装材として使われているものなんです。それをノートブックにしてみたり、今は、経木を使ったお皿も考えていたりしています。


興梠 ユニークな提案だなあ。
奥田 僕が好きな話に、「茶碗を変えたら生活が変わる」というのがあるんですけど。いい茶碗を買ったら、茶碗が今まで使っていたテーブルと合わなくなって、テーブルを合うものに変えたら今度は椅子まで変わっちゃった、みたいな話です。
僕は、クラフトでつくられたものを置くと、そういうふうに生活を変えていく作用が起こりやすいと思っていて。なぜならクラフトでつくられたものは、均一でできている工業製品にはない不均一さがあるから。均一と不均一って相性が悪いんですよ。のっぺりとしたテーブルに不均一な茶碗が乗ると、なんか気持ち悪い感じがするじゃないですか。
その違和感からたとえば、「もっとどういうものを使ったらしっくりくるだろうか?」と考え、テーブルをクラフトの不均一なものにしたとする。その結果、その人の気持ちよさにつながったら、それは自然と人がいい形でつながっているということだと思うんです。
── 「どういうものを使ったら心地いいだろう?」と考えること自体が、家具に使われている素材とか、それをつくる人とか、それが生まれる環境とかへの関心になって、頭で考えるよりも感覚として自然と森へと近づいていく流れが生まれていると言えますよね。
奥田 そうですね。暮らしの中に森が取り入れられることによって、それが自分の心地よさだけでなく、じつは森への関心や森の循環の一助にもなっている。そういった森の豊かさにつながる流れを、人々の暮らしを豊かにすることからデザインしたいなと思って事業をしています。
興梠 いろんな文脈を絡めて自然と触れ合ってもらうという話は、共感する部分が大きいです。まさにistも、今の時代のキャンプカルチャーと違うのは、「キャンプっていいよね」じゃなくて、「自然の中で過ごすことっていいよね」という思いが根本にあることなんですよね。
キャンプという言葉を聞いたときに一般的に想像されることって、テントを張って屋根をつくってそこにいろんな装飾を施して……というふうに、自然の中でたくさんのギアを駆使することが目的になっている側面がある気がしていて。
でも本来キャンプって、森の中や川辺に泊まったりする手段のひとつで、その手段を使って自然を感じることが一番の価値なんじゃないかと思うんです。
 Photo by Syuheiinoue
Photo by Syuheiinoue
奥田 たしかに、「キャンプの思い出が、つくったご飯のことになりがち」みたいな話も、自然を感じながら過ごすという部分が損なわれているからかもしれないですね。
興梠 それでやっぱり、自然に近づく過ごし方というのも人それぞれだと思うので、いろんな文脈を絡めるというのはとても大切なことのように感じました。登山やクライミングなどアクティビティーに寄りすぎちゃうと、専門性が高くなるだけでなく日常の中に持ち帰りづらいので、なんでしょうね、たとえば森の中で音楽を聴くとか。
奥田 いいですね。
興梠 「普段も音楽を聴いているけど、森の中で聞いたらもっと気持ちよかった」みたいな瞬間があると思うんですよね。それで、家に帰ってきたら、普段、音楽を聴いたりしながら過ごす部屋に花を飾りたくなるかもしれない。そういう日常に落とし込みやすい文脈を絡めて、ひとつの場をつくっていきたいなと思いました。
奥田 やまとわも「森は人を幸せにするか?」という問いの中で事業をやっているので、istが「森が人々に対してどんな価値を提供できるんだろう」とか「森はどんな心地よさをつくれるんだろう」ということで見えてきたものをまた、教えてほしいですね。